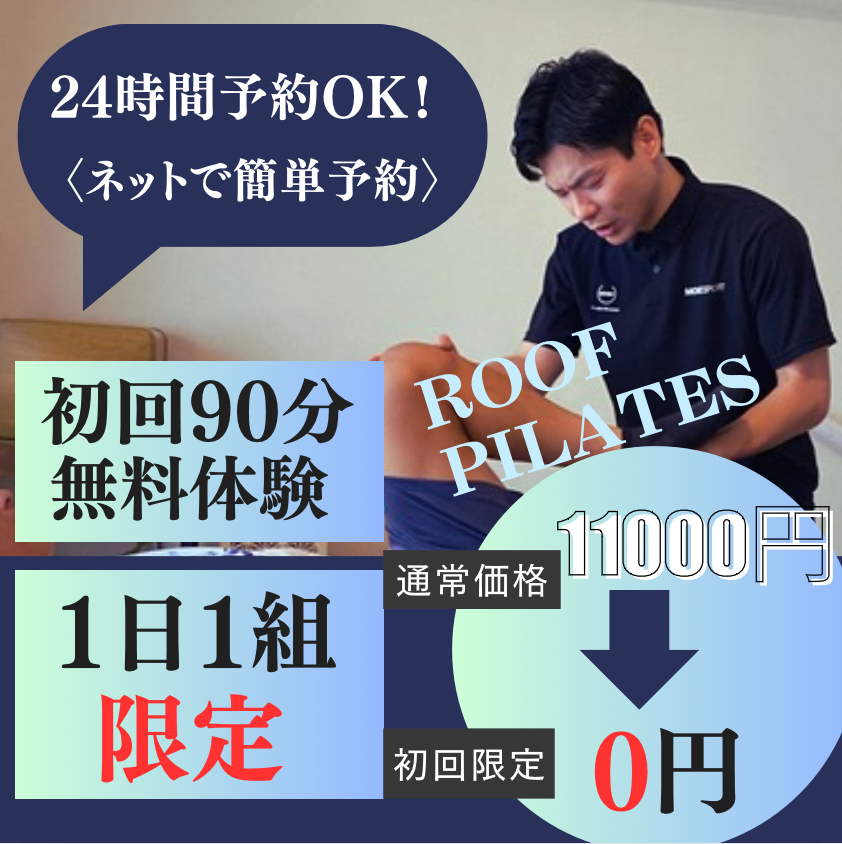中高生の不登校は年々増えており、保護者や学校関係者にとって大きな課題となっています。
「どうすれば学校に行けるようになるのか?」「家庭でできるサポートは?」と悩むことも多いでしょう。
不登校の背景はさまざまで、解決策も一つではありません。
この記事では、不登校の原因を整理しながら、家庭や学校でできる具体的なサポート方法を解説します。
不登校の主な原因とは?
不登校の原因は一人ひとり異なりますが、大きく分けると以下のような理由が挙げられます。
1. 学校の人間関係の悩み
・クラスメイトや先生との関係がうまくいかない
・いじめや仲間外れにされている
・グループ活動や発表が苦手でストレスになる
2. 学業の負担やプレッシャー
・授業についていけない、勉強がわからない
・成績が悪く、先生や親に叱られるのが怖い
・受験や進路へのプレッシャーが大きい
3. 心や体の不調
・朝起きられない、体がだるい(起立性調節障害の可能性も)
・ストレスで頭痛や腹痛が続く
・うつや適応障害などのメンタル面の問題
4. 学校の環境が合わない
・校則が厳しすぎる
・部活動の負担が大きい
・授業の進め方が合わない
5. 家庭の問題
・親の期待が大きくてプレッシャーを感じる
・家庭内でのトラブル(夫婦喧嘩、離婚、経済的な問題など)
・過干渉や過保護にストレスを感じる
家庭でできる不登校のサポート方法
不登校になったとき、まず大切なのは「家庭での対応」です。
無理に登校を強制せず、子どもに寄り添いながら、少しずつ前進するサポートが必要です。
1. まずは「休んでもいい」と認める
「学校に行かせなきゃ」と焦る気持ちはわかりますが、無理に登校を促すと逆効果になることが多いです。
まずは、「休むことも大切」と伝え、安心できる環境を作ることが重要です。
「大丈夫だよ」「あなたのペースで考えよう」と声をかけることで、子どもも少しずつ気持ちを落ち着かせることができます。
2. 子どもの気持ちを否定せずに聞く
「なんで学校に行かないの?」と責めるのではなく、「今どんな気持ち?」と優しく聞くことが大切です。
不登校の理由が明確でない場合も多いので、無理に答えを求めず、子どもが話したいときに話せる環境を作りましょう。
「どうしたい?」「何があれば安心できる?」と選択肢を提示すると、少しずつ前向きになれることもあります。
3. 朝のプレッシャーを減らす
不登校の子どもにとって、朝は特にプレッシャーを感じやすい時間です。
・「早く起きなさい」「遅刻するよ」と責めるのを控える
・学校に行く・行かないに関係なく、朝ごはんを一緒に食べる
・「今日はどうする?」と子どもの意思を尊重する
など、朝の時間を穏やかに過ごせるように工夫しましょう。
4. 生活リズムを整える
不登校が続くと、昼夜逆転してしまうことがあります。
・夜更かしを避け、少しずつ起床時間を整える
・昼間に軽い運動をする(散歩やストレッチなど)
・日光を浴びる時間を増やす
など、無理のない範囲で生活リズムを整えることが大切です。
5. 外とのつながりを持つ
学校に行かなくても、家の外に出る機会を増やすことが大切です。
・図書館やカフェに行ってみる
・家族で買い物や散歩に出かける
・習い事やオンライン学習を試してみる
など、少しずつ外の世界に触れる機会を作りましょう。
学校でできる不登校のサポート方法
学校側も、不登校の生徒をサポートする体制を整えることが重要です。
1. 無理に登校を強制しない
「学校に来なさい」と圧力をかけると、かえって登校が難しくなります。
まずは、「今は休んでもいい」「学校以外の方法もある」と伝え、安心感を持たせることが大切です。
2. 別室登校やオンライン授業の活用
教室に入ることが難しい場合、別室登校やオンライン授業の活用を提案するとよいでしょう。
・保健室や相談室で授業を受ける
・個別指導や家庭学習のサポートをする
・オンラインで授業を配信する
など、子どものペースに合わせた対応が必要です。
3. 学校以外の選択肢を紹介する
学校が合わない場合、フリースクールや通信制高校という選択肢もあります。
・フリースクール(自由な学びの場)
・適応指導教室(自治体が運営する不登校支援施設)
・通信制高校やサポート校
など、子どもが自分に合った環境を見つけられるように情報提供しましょう。
まとめ:不登校は「その子のペース」で改善する
不登校は決して「怠け」や「甘え」ではありません。
無理に学校に行かせようとするのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら、少しずつ「社会とのつながり」を取り戻すことが大切です。
家庭と学校が協力し、子どもが安心して成長できる環境を整えていきましょう。